障害年金について
障害年金とは、病気やケガによって働くことや日常生活に支障が出た場合に、一定の条件を満たせば受け取ることができる公的年金制度です。これは高齢者が対象となる老齢年金とは異なり、20代や30代などの若い世代でも申請・受給の対象になります。
それではここで、障害年金の専門家「社労士サトメグ」と、サポートキャラクター「ココロかっぱ」が、障害年金についてわかりやすくご紹介いたします!
サトメグとココロかっぱの障害年金教室
Chapter1 年金は歩いて来ない だから請求するんだよ ♡
アイコン.png)
サトメグさん!そもそも障害年金って何なんですか?
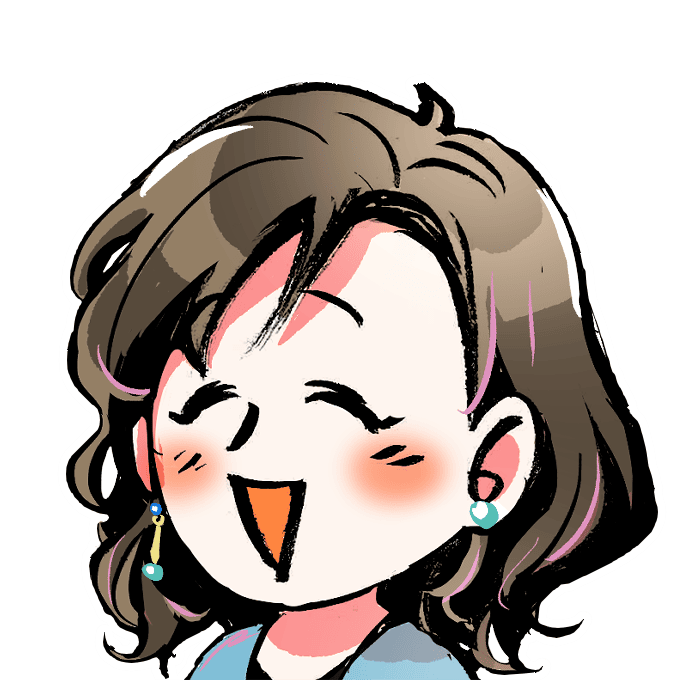
障害年金というのは病気やケガなどで、仕事や日常生活に支障が生じるときに
・ 初診日要件(障害の原因となった病気やケガの最初の診察日が明確であること)
・ 保険料納付要件(一定期間、年金保険料を納めていること)
・ 障害状態要件(障害の程度が定められた基準を満たしていること)
の3つの条件を満たせば受給できる公的年金制度のことだよ。
お年寄りの老齢年金とは違って、20代や30代の若い人でも対象になるの
アイコン.png)
それって、ケガしたり、病気になってしまったら、病院や役所からお知らせか何か来るんですか?
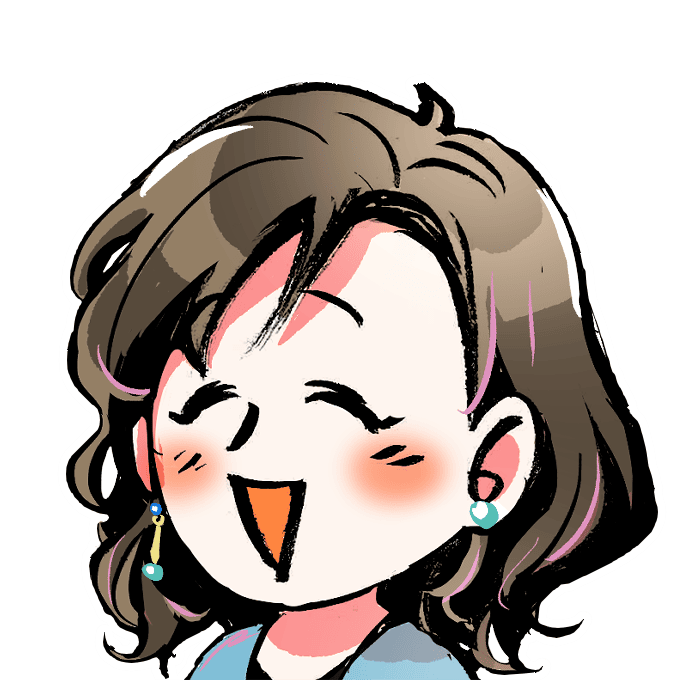
ううん、障害年金に関するお知らせはどこからも来ないの。障害年金を受給するためには、本人が自分で申請手続きをして、障害の程度や状態について年金機構などの認定を受ける必要があるんだよ。つまり、『待っているだけでは受給できない制度』なの。
アイコン.png)
えぇ⁉それじゃあ、自分がもし病気になっても該当するのかどうかわからないじゃないですか?どんな状態になったら該当するんですか?
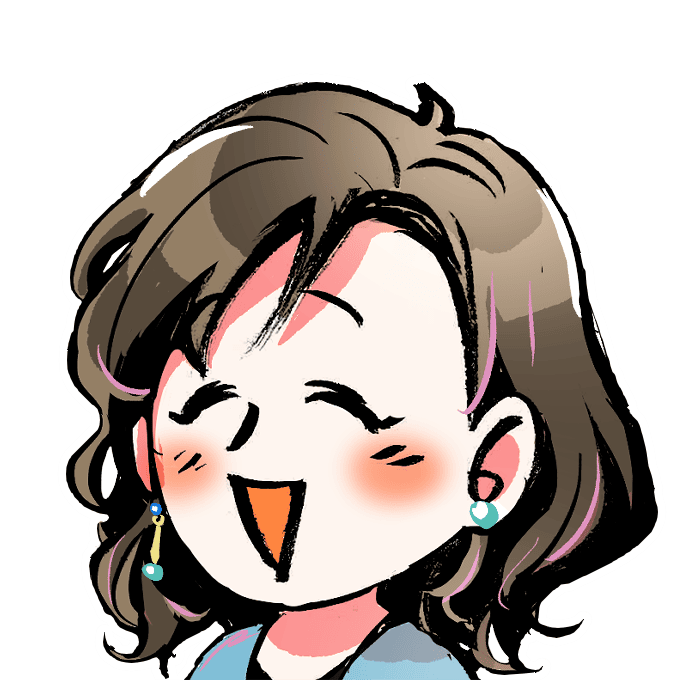
障害年金には、障害の程度に応じた細かい認定基準というものがあるんだけど、まずは日本年金機構に請求して診査してもらわないと実際に該当するかどうかはわからないの。だから、上の3つの要件を満たして、初診日から1年6ヶ月(※障害認定日)が過ぎているなら、まず請求してみると良いよ。
アイコン.png)
なんか難しそうだな・・・どこで何をすることから始めればいいんですか?
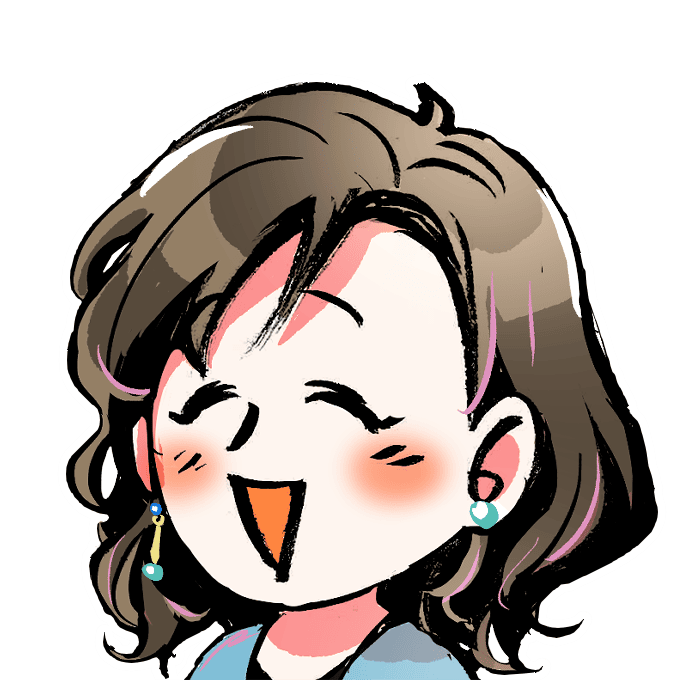
まずは、お近くの年金事務所に相談に行って、発病から現在に至るまでの経緯を詳しく話して、初診日を明確にして、当時の保険料納付要件を満たしているかどうかの確認を受けます。そのうえで、初診や現在それぞれの医療機関に診断書の作成を依頼し、病歴・就労状況等申立書などの必要書類作成もしなくっちゃいけないんだよ。
アイコン.png)
あぁ~なんだか聞いてるだけでわけわからなくなってきた・・・今の病院にたどりつくまで何年間もかかったり、複数の病院にかかっている場合もありますよね?どこが初診日なのか……?
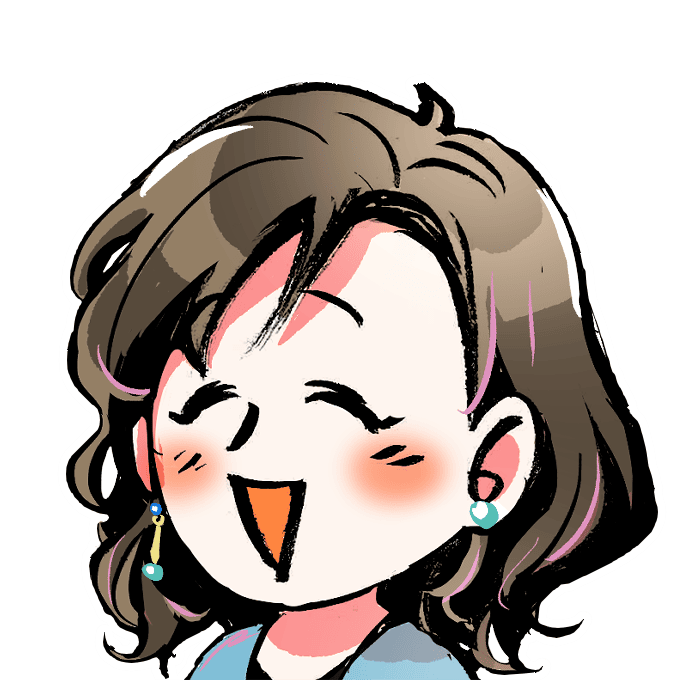
初診日が不明確なままで障害年金を請求すると、症状が重くても不支給になってしまう場合もあるの。初診日は障害年金を請求する上で非常に重要なポイントなんだよ。たとえ途中で転院したとしても、年金制度上はそのご病気の症状で「初めて医師の診療を受けた日」を初診日とします。だから病名が長い期間はっきりしなった場合は、現在の病気と因果関係のある症状がいつ頃からあったのかを丁寧に確認する必要もあるかな。
アイコン.png)
も~~~何をどうすれっていうのか・・・

大丈夫だよ!そんなときこそ、まずは私に連絡をちょうだい。昔のことなんてなかなか覚えていなくて当然。でも、お話しているうちに少しずつ思い出してくれたり、糸口が見えてきたりすることもよくあるの。私が初診の確認から一緒にやるので、最善の策を一緒に考えます!
アイコン.png)
そうか!まずは一歩動き出さなきゃですね!
なんとなくご理解頂けましたか?「とりあえずもう少し詳しく聞きたい」と思った方は、こちらのお問い合わせフォームから、ご連絡ください。
Chapter2 障害年金は初診日が命!
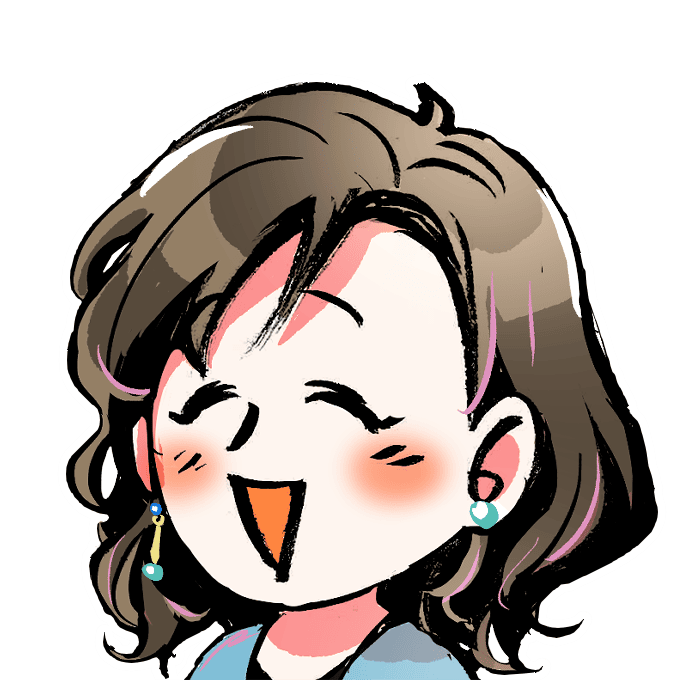
さあ、ここからは、より専門的な解説もしていくよ!準備はOK?(笑)
アイコン.png)
は、はいぃぃ!!

障害年金は初診日が命!!!なの
アイコン.png)
えぇぇ?いきなり、そんなこと言われても・・・

少し専門的な言葉でいうとね『初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日』をいいます。ここで大切なのは、「診断名が確定した日」ではなく、症状について最初に診療を受けた日であるという点です。これが障害年金の申請における重要なポイントとなります。じゃあどうしてそんなに初診日が大事なのか、ちょっとコチラを見てね
アイコン.png)
わわっっ!!なんかメグミさんすごい!社労士みたい!!!

一応社労士でんがな・・・これでも障害年金業務に(勤務時代も入れて)13年間携わってんのよ…
アイコン.png)
もっと尊敬することにします!

してなかったんか~い…
アイコン.png)
ちゃ~んとしてますよ~ん(笑)
Chapter3 まだある⁉受給の条件
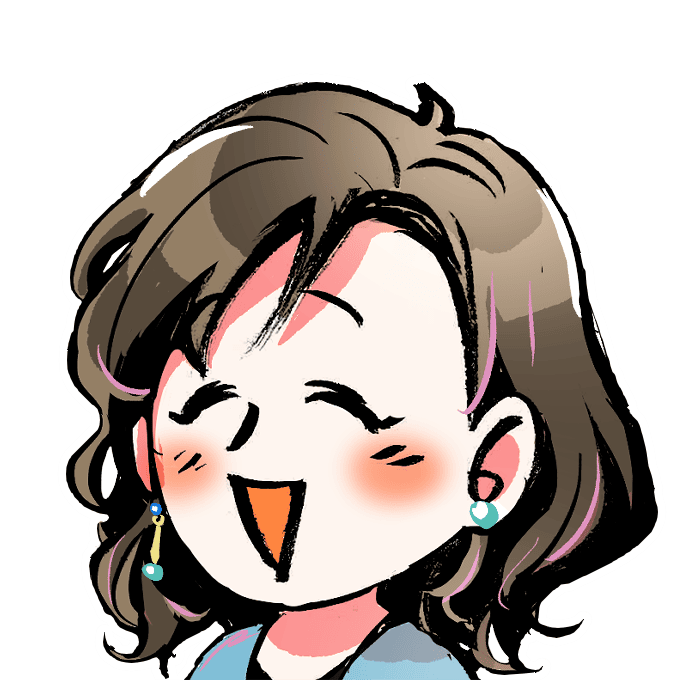
さてさて、そして、もう一つの大事なポイントが保険料納付要件というのだけどね。これも条文には難しく書かれているのでそのままいうと
「初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの保険料の納付状況」を確認するの。
保険料納付要件を満たすには、次のいずれかを満たす必要があります:
・初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
・または、初診日の属する月の前々月までのすべての被保険者期間において、未納期間が3分の1未満であること
アイコン.png)
???

これはね、いくら自分で何かを調べてもわからないかもしれない。余程、年金定期便などをきちんとまとめて取っておいてる人とか、一回も転職せず学生時代から一つの会社で働いている人とかね。だから、ここは素直に年金事務所で納付要件を調べてもらうのが一番早いです。
アイコン.png)
なるほど!
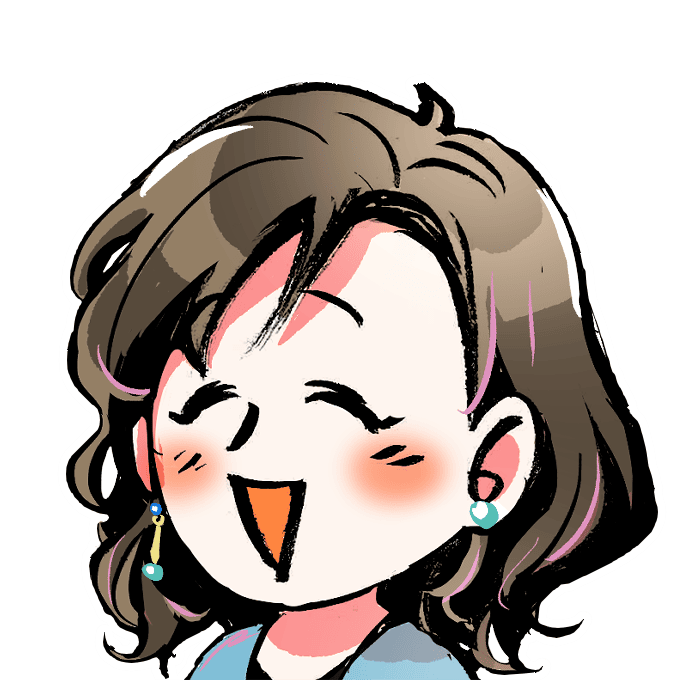
最後にもう一つ重要なのが、障害認定日についてです。障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日のことを指します。
この障害認定日を過ぎていれば、原則として障害年金を請求することが可能です。
もし障害認定日の時点で障害等級に該当していなかった場合でも、その後65歳に達するまでの間に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合には、その時点で障害年金のすることができるから、まずは、一度チャレンジしてみるのがよいと思うよ!
もちろん、障害年金を請求したからといって、必ず受給できるわけではありません。障害年金の支給は、ご病気や障害の程度が障害等級に該当しているかどうかによって判断されるからです。障害の状態が、国の定める障害等級(1級・2級・3級など)に該当することが受給の条件となりますので、診断書や申立書の内容もとても重要です。そのため、事前にしっかりと準備を整えて、正確な情報を提出することが、障害年金受給の可否を左右する大きなポイントになります。
障害認定基準について
障害年金には、それぞれのご病気ごとに「国民年金・厚生年金保険認定基準」があり、現在は令和4年4月1日改正のものが最新となっています。障害年金は、原則的にこの認定基準にのっとって診査をされますので、まずはご自身のご病気がこの認定基準と照らし合わせてどのくらいの程度であるのか、確認をされるとよいですね。
現在の認定基準は日本年金機構のホームページを参照して下さい。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
また、それぞれのご病気や障がいの具体的な申請の方法等については、事例・実績のページをご参考にしてください。
Chapter4 年金請求はまだだけど、これだけはやっておいて♡
アイコン.png)
サトメグさん!まだまだ年金請求するくらいにはなってないけど・・・将来のこと考えて、今からやれることってあるんですか?
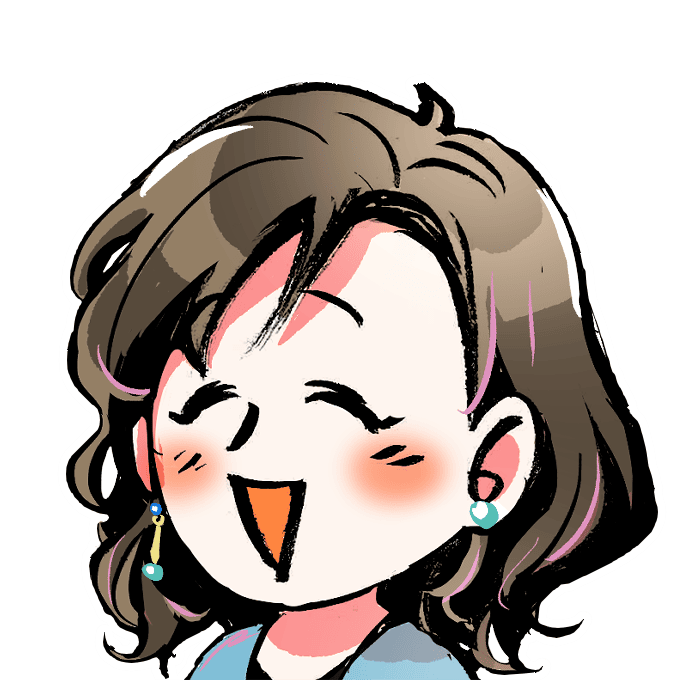
まずは初診日から1年6ヶ月が経過するというのが大原則なんだけど、1年6か月経っていたとしても、今はまだ程度的に年金請求するに至っていないと思うけどな~という場合もあるよね。もちろんそのまま悪くならない方が絶対にいいのだけど、進行性のご病気の場合は将来が不安という人も多いの。そんなときはこれだけはやっておいて!というサトメグからのとっておきのアドバイスをご紹介します。
カルテの保存義務は5年!
いざ、障害年金請求をしようとしたときには、既にカルテの保存義務が切れており、医証を入手できない。廃院している。ということもよくあります。今はまだ年金請求の時期ではなくても、医療関係の書類(領収証、お薬手帳など)は捨てずにまとめておいてください。
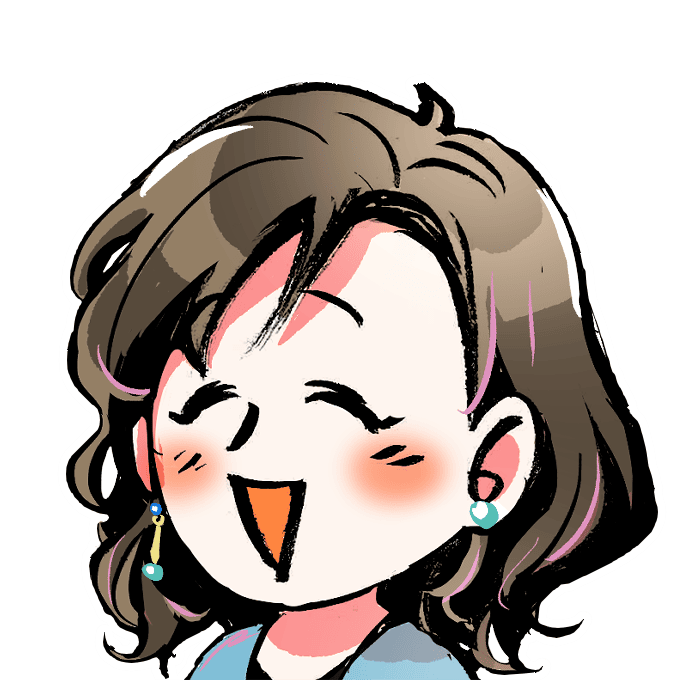
きちんとしたファイリングが苦手なら、何か一つの段ボールかなにかの箱にポンポンと入れて置くだけでもいいです。時期が来たら、箱ごと持ってきてください(笑) 一緒に探しましょう。
主治医ときちんと話ができるようにしておくこと!
普段の診察での医師との関係性、コミュニケーションは、ご自身の障害状態を的確に反映した診断書を書いていただく上で非常に重要です。当たり前のことですが、定期的な受診(予約したらきちんと受診する)、きちんと自分の症状等を診察で伝えるなど、心がけてください。
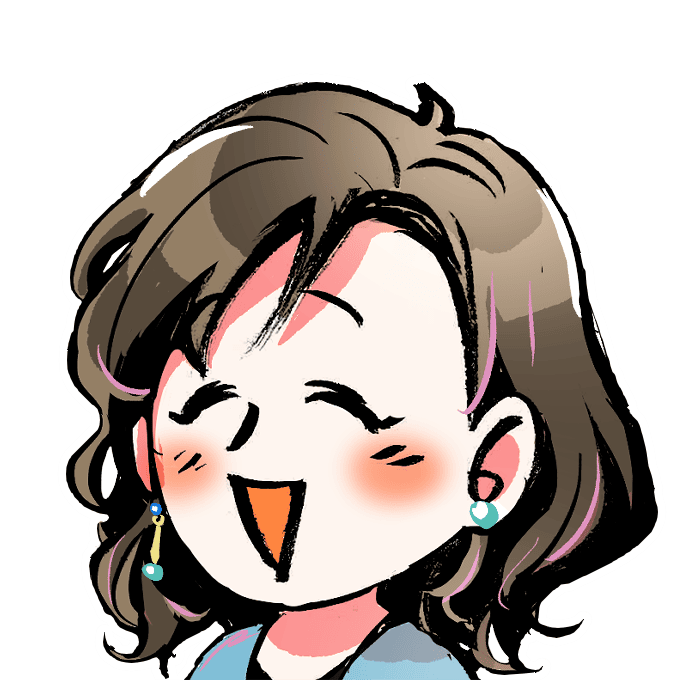
実際に年金診断書等を依頼する際、どうしても医師に上手く話せないという時は、最善の策を一緒に考えて、できる限りのお手伝い(日常生活の様子を文章にまとめる等)をします。
ご家族にも申請手続きの協力を!
ご自身が動ける状態、話せる状態であればいいのですが、そのご病状から思うように外出等ができない場合もあります。進行性のご病気で少しずつできないことが増えていってしまうこともあります。どこに何を締まっているか、普段からご家族や気を許せる相手には古い診察券やお薬手帳の場所等を教えておくというのもよいですね。
ご自身ではどうにもならないときは、ちょっとだけご家族に頼っちゃいましょう。もちろん、ご家族の方のみの相談も多数お受けしています。
アイコン.png)
ご自身ではどうにもならないときは、ちょっとだけご家族に頼っちゃいましょう。
もちろん、ご家族の方のみの相談も多数お受けしています。
初診から現在までの病院歴をまとめておくこと!
今はまだ年金請求をするのは早いかな・・・としても、人の記憶は何年もすると薄れ、曖昧になっていきます。日記とまではいかなくても、要所要所で何か大きな転換期があったらメモ等に残しておくクセをつけておくとよいです。 治療内容が変わった、薬が変わった、その他、職場が変わった、勤務形態(時間等)が変わった、引っ越した等、治療にまつわることだけでなく、自身を取り巻く環境を書いておくこともいいですね。
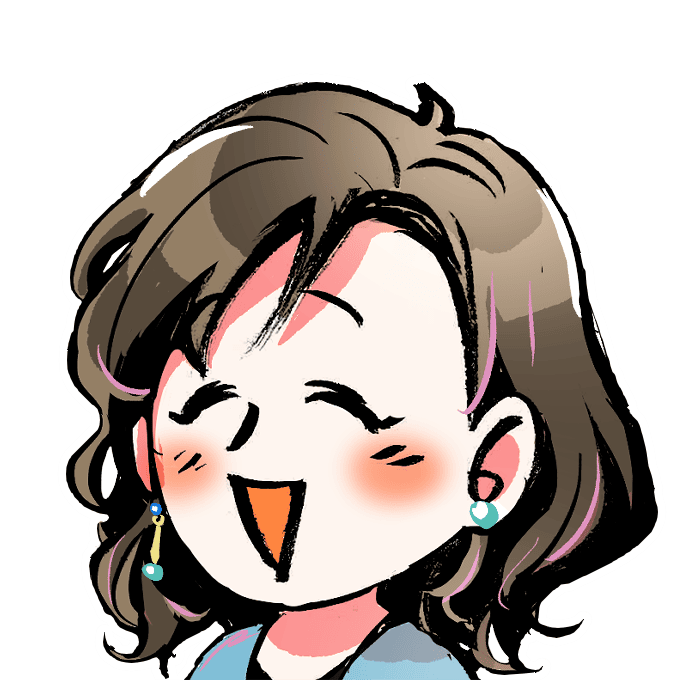
どう?そんなに難しいことではないでしょう?
今はまだ障害年金の請求時期ではないけどという方も、まさかの将来に備えて、このくらいのことを最低限やっておくといいと思うよ。
アイコン.png)
わかりました!
自分でも病院の診察券とか、もう少しきちんと管理しようと思いました。将来のことはわからないです。
Chapter5 障害年金の手続きの流れってどのような感じ?診断書や申立書って?
アイコン.png)
実際に障害年金手続きをしよう!と思い立ったらどうしたらいいんですか?
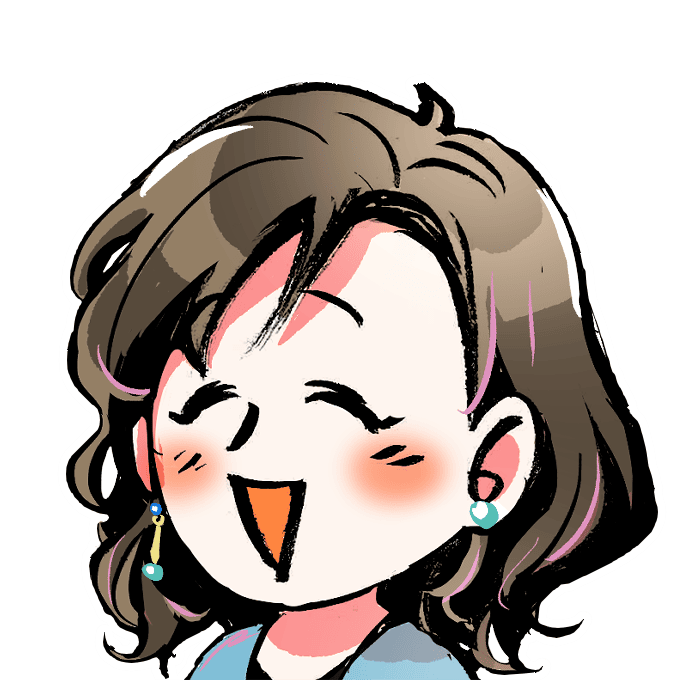
まずは、初診日がどこか調べることが一番最初にやるべきことだよ!
初診日の大切さはさっきも説明したよね。具体的には、こんな感じで進めます。
STEP.1 初診日を調べる
今はまだ年金請求をするのは早いかな・・・としても、人の記憶は何年もすると薄れ、曖昧になっていきます。日記とまではいかなくても、要所要所で何か大きな転換期があったらメモ等に残しておくクセをつけておくとよいです。 治療内容が変わった、薬が変わった、その他、職場が変わった、勤務形態(時間等)が変わった、引っ越した等、治療にまつわることだけでなく、自身を取り巻く環境を書いておくこともいいですね。
アイコン.png)
わかりました!障害年金は初診日が大事!!もう耳タコ状態ですが、わかりました!
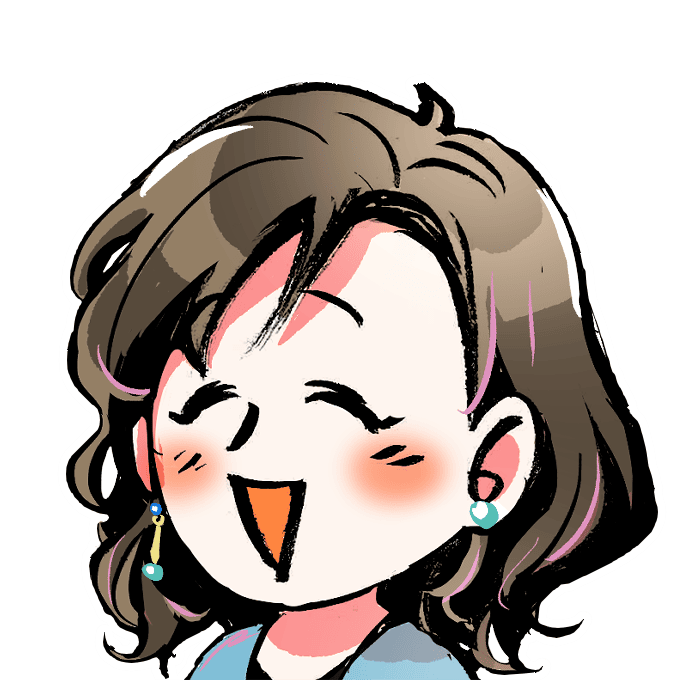
しつこくてごめんねぇ(笑)
初診日が特定できて、保険料の納付要件なども満たされているならば、いよいよ診断書の依頼だよ。
STEP.2 医師に診断書の作成を依頼する
初診日が分かり、初診の時点で保険料納付要件が満たされていたという事実がわかった場合、障害年金の手続きに進むことができます。
診断書は全部で8種類あります。
診断書の種類
- 眼の診断書
- 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の診断書
- 肢体の診断書
- 精神の診断書
- 呼吸器疾患の診断書
- 循環器疾患の診断書
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の診断書
- 血液・造血器・その他の診断書
アイコン.png)
あわわ...そんなに種類があるんだ!
どれを使えばいいのかは教えてもらえるのですか?

通常は一つの傷病に1枚の診断書。年金事務所等で、必要な書類をもらえるよ!でもね、ご病気によっては複数の症状がある場合もあるでしょう?例えば脳出血による後遺症で『肢体の麻痺』と『言語障害』と『高次脳機能障害』もあるとか・・・そんなときは状況によって2種類、3種類を同時に出すこともあるよ。そして、障害認定日(初診日から1年6ヵ月)での請求なのか、事後重症(最新の症状)での請求なのか、時期に応じて枚数も変わるので、注意が必要だよ。
アイコン.png)
はい、なんとなくわかったよ~な・・・

はい、わかったらどんどん行くわよ~
STEP.3 『病歴・就労状況等申立書』の作成
アイコン.png)
あぁ~それ、それです!
なんかすっごくめんどくさそうで、何書いたらいいかわかんないし、的外れな話書いちゃいそうだし・・・
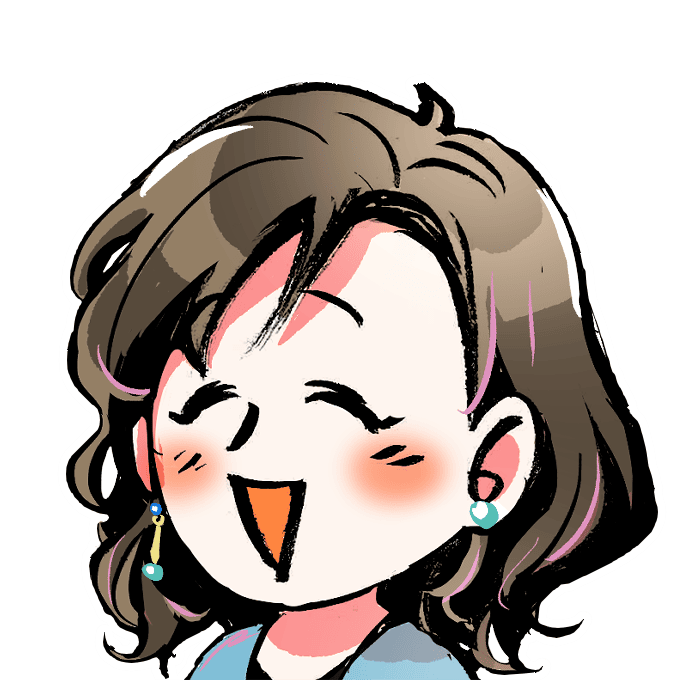
この「病歴・就労状況等申立書」は、医師に書いてもらう診断書ではわかりきれない日常生活の大変さ、これまでの状況等を書くことが大事なの。例えば・・・
「病歴・就労状況等申立書」項目の例
- 発病の時期
- 発病時の状況
- 治療の経過
- 入院、退院、転院
- 治療の中断・再開
- 就学や就労の状況
- 作業所利用
- ヘルパー利用の状況
- 生活でどのような支障がでているのか
アイコン.png)
や、やだ、もうムリ・・・私なら書けない・・・
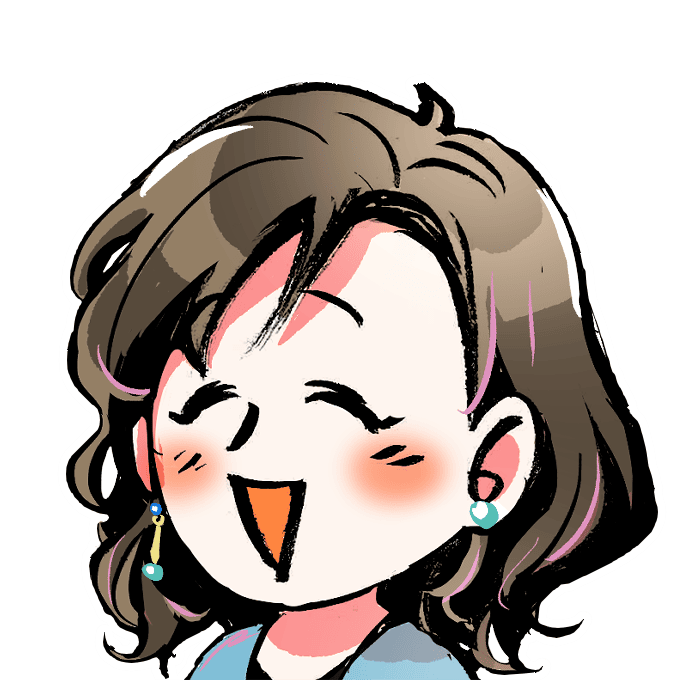
大丈夫!そんなときこそ、私に連絡して!盛り込むべき内容が多いけど、丁寧に書く必要があるので、申立書はとっても大事な書類なの。そして、なんでも安心してお話してください。ご来所でも、メールでも、LINEでも、Zoomでも、うちの事務所と話すときはリラックスしてほしいです。大体の人は雑談しているようだったって言ってくれてます(笑)
障害年金の手続き代行はご連絡ください
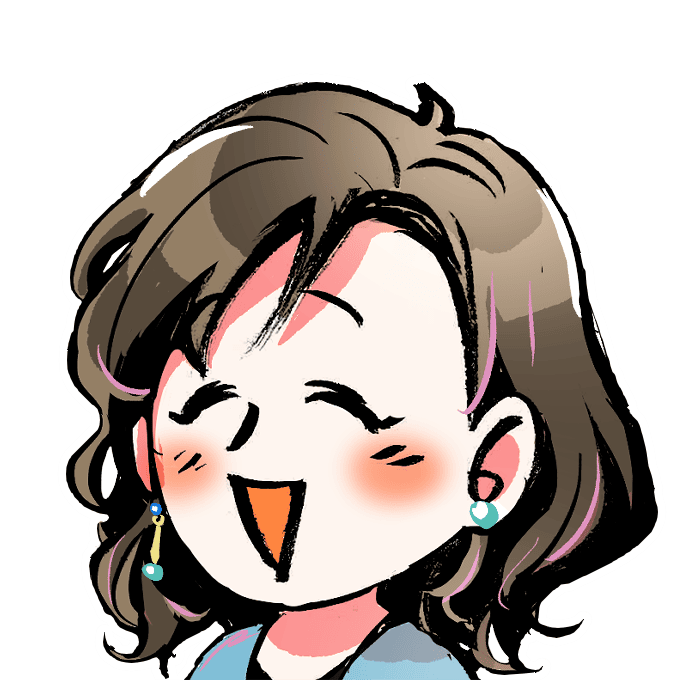
いかがでしたか?専門的な部分は、少し難しかったかも知れませんね。
繰り返しですが「とりあえず相談したい」と思った場合は、こちらのお問い合わせフォームから、ご連絡ください。